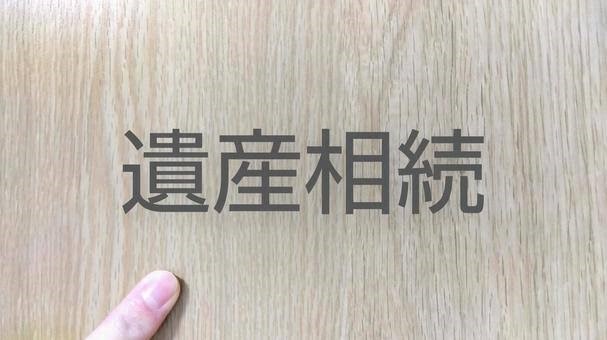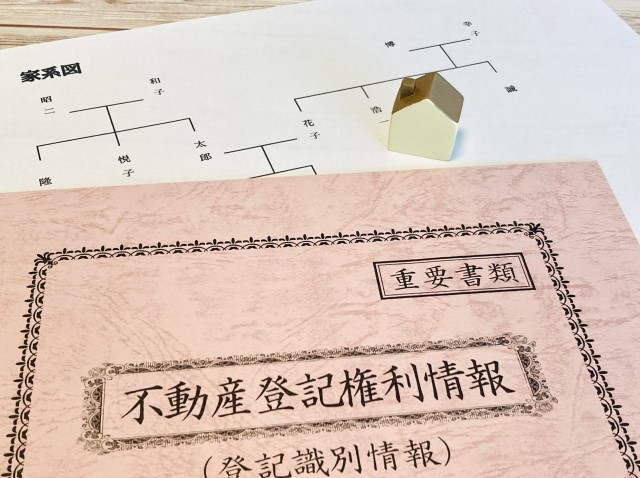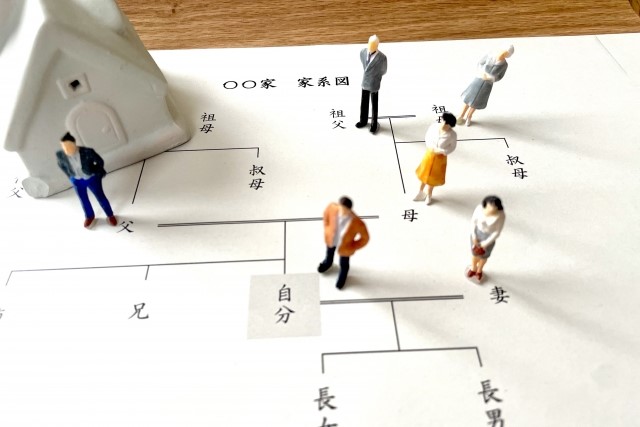こんにちは!
ヤーマンです!
特に戸建ての相続の場合に聞かれる質問の中に「家の前に細い道があるんだけど、相続の手続はしたほうがいいの?」というものがあります。
戸建てが並んでいるエリアには、国道や県道などではない細めの道路があることが多いのですが、これはそれぞれのお家によって事情が異なります。
今回は相続の手続が必要か見分ける方法をお話ししていきたいと思います。
自宅前の道はだれのものか
さて、自宅前の道はだれのものでしょうか?これはケースバイケースです。
家の持ち主と同じ場合もあれば、近隣の複数の家の持ち主が共同で所有している場合があります。さらには市区町村など公のものというケースもありますので、調べてみないと何とも言えません。
自宅前を通る道の持ち主が家の持ち主と同じ場合であれば、家の持ち主が亡くなった際には家と道の両方に相続手続が必要となります。
また家の前の道を複数の人が共同で所有している場合でも、家の所有者が亡くなった時には、家の所有者の持ち分に関して相続手続を行います。
誰のものか調べる方法
「家の前の道が誰のものか、まったくわからない」というお宅も珍しくないと思います。普段そういった話はあまりしないからです。
その道路の所在地がわかる場合には、法務局に行くと登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができますので、登記簿謄本(登記事項証明書)を見ると、所有者がわかります。
もし、「家の所在地はわかるけど、道路の所在地がわからない」という場合、その地方を管轄する法務局に行き、「〇〇番地の前の道の地番が知りたい」ということを法務局の職員に伝えてみることをお勧めします。
法務局にゼンリンの住宅地図が置いてある場合、そちらを見るように案内されるかもしれません。調べると、道路の地番がわかりますので、そのうえで登記簿謄本(登記事項証明書)を請求して所得することが出来ます。
もしゼンリンの住宅地図がない場合、「公図」という書類を取るように勧められるかもしれません。この公図にも地番が書かれていますので、公図で地番を確認したうえで登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することが出来ます。
最後に
今回は家の前の細い道に相続手続が必要な場合をお話ししました。
時折、自宅と土地の相続手続は行っても、道路は持ち主がそのままというのは時折見かけますが、そのまま放置すると、後に相続人が困ることになります。念のため自宅前の道が誰のものか、確認されるのもよいと思います。